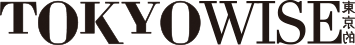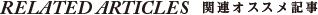2016.02.19
- BIRTHDAY STORIES
-

Birthday Stories Vol.11
『その薄紅のはんぶんの』
日野 草
「……何かあったの?」
テーブルについた彼女に、勇気を振り絞って訊いてみた。
彼女は、ふう、と息を吐く。
休日午後のスターバックス。郊外とはいえ、座席を確保するのは大変だった。見せたいものがあるんだ、と言われて来たのだが、向かい合って五分ほど。彼女は一言も喋らない。
時折、出入り口のほうを窺っている。
どうにも挙動不審だ。
これは、あれかもしれないな。ぼくは心を雑巾のように絞り、垂れてきた勇気を掻き集めて、質問の冒頭を舌にのせた。
「ぼくと――」
ぼくと別れたいのか?
思い当たることがある。ぼくらは共に、今年の春から大学三年生だ。将来が見えて来る時期だ。お互い入学してすぐに付き合い始めて、なんだかんだと今まできたが、学生時代の気楽さが薄れつつある今、彼女の心境に変化が起きても不思議ではない。ぼくは大学院へ進む決意を固めている。彼女は就職の道を選んでいる。この先、価値観がずれていくことだって想像できる。それを見越して早めの決断をしたのかもしれない。
ところが彼女はぼくの質問を聞いていなかった。
ちょうど店のドアが開いて、彼女はそちらを振り返ったからだ。
ぼくもおなじ方向を見た。妙に姿勢のいい、白髪のおじいさんが店に入って来たところだった。杖をついた小柄なおばあさんと腕を組んでいる。
「あっ」
叫ぶなり、彼女は腰を浮かしかけた。思いとどまって席についたものの、肩が大きく上下している。
「な、何?」
当惑したぼくに彼女は顔を戻した。完全に笑顔。
「良かったー、逃げたかと思ったー」
逃げる?
いったい何のことだ?
「あの二人ね、あたしのおじいちゃんとおばあちゃんなの!」
僕の顎はテーブルの上に落下しそうになった。
気を使ったのかもしれない。バリスタさんがわざわざカウンターの中からやって来て、二人を近くのテーブルに案内した。
お年寄り二人はスマートフォンを取り出した。たどたどしい手つきで、おばあさんが操作している。おじいさんも自分のスマートフォンを握り、叩いた。
 注文を終え、やがて二人分のドリンクが並んだ。マグに注がれたキャラメルマキアート。
注文を終え、やがて二人分のドリンクが並んだ。マグに注がれたキャラメルマキアート。
可愛い名前ね、とおばあさんが言っているのが聞こえる。二人はそれを嬉しそうに受け取り、向かい合った。
「おばあちゃんはね、足を悪くしてから出不精だったんだよ。だからおじいちゃんはなんとか外に連れ出したかったんだって。何をしたらいいか? って相談されて、スタバのeGiftをすすめたの。もうすぐおばあちゃんの誕生日だったから」
「じゃあ、今日は……」
「そうなの」
こちらを向いた彼女は微笑んでいた。その顔を見て、ぼくはちょっと驚く。誤魔化すために、手元のカフェミストに口をつけた。
「スマホで飲み物を買うなんて初めてだし、スタバにも来たことがなかったから、おばあちゃんが怖気づいて断るんじゃないかと思ってたけど、成功して良かった。いい光景でしょ? これを君に見せたかったんだ。なんか最近の君、ちょっと落ち込んで見えたからさ」
ぼくは彼女の肩越しに、ドリンクを味わう二人を見た。
皺くちゃな顔いっぱいに笑顔を浮かべているおばあさんと、まっすぐな背中で微笑んでいるおじいさん。二人はどのくらい、この薄紅の季節を一緒に過ごしてきたのだろうか。何度も危ないことはあったに違いない。ケンカだって、人生の変遷だって……。
それを乗り越えて今日、また、新しいことに挑戦したのだ。
ぼくは彼女を見た。
微笑む顔は、やはり、あのおばあさんに似ている。
「ねえ」ぼくは、思い切って言った。彼女は一月生まれだから……。「来年の君の誕生日、ぼくも贈っていいかな」
彼女は瞬きをした。
「そしたら君の誕生日には、あたしが贈ってあげよう。あ、君は八月生まれじゃん。あたしが贈るほうが先になるね」
ぼくたちは顔を見合わせて笑った。素敵な時を過ごすお二人の、その薄紅の季節の半分でも一緒に過ごすこと。今日からそれが、ぼくの目標になりそうだ。
日野草
1977年東京都生まれ。2011年『ワナビー』で第2回野性時代フロンティア賞を受賞しデビュー。著書に、『GIVER』『BABEL』がある。