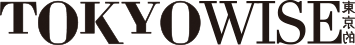映画『不機嫌なママにメルシィ!』
監督・脚本・主演、ギヨーム・ガリエンヌに
インタビュー(2)
2014.10.02
- CLIPPING
-

──舞台を観た観客の反応はいかがでしたか?
驚くほど大きな反響があった。最初はオリビエ・メイヤーの劇場で、12回だけ公演して終わる予定だったんだ。だけど口コミで噂が一気に広まって、パリの「Théâtre de l’Athénée(アテネ劇場)」という由緒正しい劇場で再演することになったり、モリエール賞という演劇賞を受賞して、また再々演することになったり。大成功だったと言えるんじゃないかな。とにかく観客席の笑いがすごかったのと、芝居が終わったあと、ぼくの楽屋を訪ねてきてくれる人たちの数もまたとんでもなくて、これならもうちょっといけるんじゃないかと思った。映画に翻案してみるのはどうかなって。
ワンマンショーをやりきった感もあったね。ひとりでおなじ演目をずっとやっていると、どうしても次はこれをこうするというのがわかってきて、精度が高まりすぎてしまうんだ。それってたくさん稽古を積み重ねてきた“結果”でしかなくて、“現在進行形”じゃなくなってしまう。もちろんなにかを作り上げるとき、稽古というのは欠かせないものだけど、一度会得したら手放さないといけない。ぼくは現在進行形のものにしか興味がないんだ。
午前はママ、午後はギヨーム
──ギヨームさんが考える舞台と映画のちがいってなんでしょう。
映画では完全に自分を投げ出さなきゃいけない。監督を信頼してついていく感じだね。自分でコントロールできる部分が、舞台よりも圧倒的に少ないから。たとえばカメラが、自分をどういう風に撮っているのかはわからないし、編集のところでどういう場面がカットされているのかもわからない。演じる側としては、そういうことを一切コントロールできないんだ。それが舞台の場合は、前もって演出家と稽古をするわけだけど、幕が開いて舞台に立ったら、そこにいるのは自分だけ。最後は自分を信頼して演じるしかない。そういうちがいがあるね。
それから舞台は、よりアスリート的な感覚を求められると思う。夜に公演があるときは、朝起きたときからコンディションを整えて、一番いい状態で夜を迎えられるようにする。公演が数日つづくときは、毎晩ライブをしているような感じだね。映画はというと、ほかのキャストもスタッフも周りにいる状況で2カ月間、ずっとライブがつづくわけだ。個人的には映画の方が疲れる気がするよ。
──舞台を映画化するにあたって、なにか苦労したことはありますか?
いや、逆だよ。この話が舞台にしか存在しないことこそ、ぼくにとってフラストレーションが溜まることだった。実際に舞台ではできなかったけど、映画ではできたことがたくさんあったんだ。たとえば裕福なブルジョワ家庭という設定。家のなかはこういう内装で、母親はこういう服を着ていて、暖炉のところにこういう花が飾ってあって、写真が置いてあって……。フランス人が“裕福なブルジョワ家庭”と聞いて、すぐに思い浮かべるいわゆるクリシェ(=紋切り型の固定イメージ)があるんだけど、そういう細かい部分を舞台ではまったく見せられなかった。
映画にはほかにもクリシェがたくさん登場する。スペインに語学留学したとき、送り込まれたのは映画とおなじように醜い街。だから現実逃避するために「ここは(ペドロ・)アルモドバルの世界なんだ」って言い聞かせながら、自分で自分を慰めたりした。スペインのところがアルモドバルの映画風なのは、そういうわけなんだ。それからホストマザーのパキには、カルメン・マウラ(注・アルモドバル作品の常連)に似ている人をキャスティングしたり、留学先のイギリスはジェームズ・アイボリーをイメージして、アイボリーの映画風に描いてみたり。これはぼく自身がもっているクリシェなんだけどね。

──今回はじめて挑戦された監督業についてはいかがでしたか?
準備と撮影自体はすごく楽しかった。だけどそのあとの編集には苦労したね。あまりにもたくさんの可能性がありすぎて、選びきれないっていうのが本音。すごく骨の折れる作業だったよ。演じながら監督すること? じつは舞台版の演出家を務めてくれたクロード・マシューが、映画の撮影現場にも来てくれたんだ。モニターを観ながら、ぼくの演出をしてくれたのは彼女ってわけ。いわばぼくの映画デビューを支えてくれた“共犯者”だね。もう監督2作目も考えていて、ぼくの女友達の身に起こった実話を映画にしようと思っているんだ。